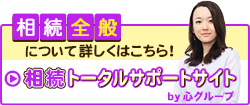こんにちは。弁護士の岡安です。
時効が5年か10年かというのは重要な問題です。
日本政策金融公庫からの借入については、5年の場合と10年の場合があります。
先日、日本政策金融公庫の時効援用の手続きの依頼を受けた際に、いざ根拠条文を考えると複雑だったので、備忘録がてら整理しました。
令和2年4月1日改正前の民法を旧民法、改正後の民法を新民法と表記しています。
1 令和2年改正後は5年
民法改正により、令和2年4月1日以降に発生した債権については、原則5年に統一されました。
新民法166条1項1号
債権者が権利を行使することができることを知った時から五年間行使しないとき。
2 令和2年改正前は原則10年
令和2年4月1日以前に発生した債権については、原則10年です。
旧民法167条1項
債権は、十年間行使しないときは、消滅する。
3 商事消滅時効で5年
旧民法下において、商行為によって生じた債権は5年の短期消滅時効が定められています。
改正前商法522条
商行為によって生じた債権は、この法律に別段の定めがある場合を除き、五年間行使しないときは、時効によって消滅する。ただし、他の法令に五年間より短い時効期間の定めがあるときは、その定めるところによる。
4 会社が行う行為は商行為
何が商行為になるかというと、会社が行として行う行為は、全て商行為(会社法5条)となります。
そのため、大抵の金融機関等が債権者となる債権は、商事消滅時効の適用により5年で消滅するという理解で問題になることは少ないです。
日本政策金融公庫も”株式会社”日本政策金融公庫であるため、会社法2条1号の「会社」にあたり、事業としての貸付であるため、会社法5条により「商行為」となり、商事消滅時効の5年が適用されることになります。
会社法2条1号
会社 株式会社、合名会社、合資会社又は合同会社をいう。
会社法5条
会社(外国会社を含む。次条第一項、第八条及び第九条において同じ。)がその事業としてする行為及びその事業のためにする行為は、商行為とする。
5 国民生活金融公庫(~2008年10月1日)時代の借入は10年
2008年10月1日に国民生活金融公庫、農林漁業金融公庫、中小企業金融公庫が解体・統合し、現在の株式会社日本政策金融公庫になっています。
国民生活金融公庫は、会社ではないため(国民生活金融公庫法2条、当時は「商事会社」)、会社法5条を理由に商行為と扱う先ほどの議論は当てはまりません。
もっとも、商法は501条~503条で「商行為」の定義を定めており、これらに該当すれば、商事消滅時効で5年の時効になります。
この点、商法501条及び同502条に列挙される行為には該当はしません。
また、信用金庫に関する判例ですが、信用金庫に営利性がないことから商人ではないとされています。
最判昭和63年10月18日
この判例の射程が国民金融公庫にまで及ぶかは定かではないですが、国民金融公庫もその目的から営利性がないため、同じく承認に当たらず、国民金融公庫時代の借入は商法503条の付属的商行為の適用はなく、時効は10年になるのではないかと思われます。
(絶対的商行為)
商法第501条 次に掲げる行為は、商行為とする。
一 利益を得て譲渡する意思をもってする動産、不動産若しくは有価証券の有償取得又はその取得したものの譲渡を目的とする行為
二 他人から取得する動産又は有価証券の供給契約及びその履行のためにする有償取得を目的とする行為
三 取引所においてする取引
四 手形その他の商業証券に関する行為
(営業的商行為)
第502条 次に掲げる行為は、営業としてするときは、商行為とする。ただし、専ら賃金を得る目的で物を製造し、又は労務に従事する者の行為は、この限りでない。
一 賃貸する意思をもってする動産若しくは不動産の有償取得若しくは賃借又はその取得し若しくは賃借したものの賃貸を目的とする行為
二 他人のためにする製造又は加工に関する行為
三 電気又はガスの供給に関する行為
四 運送に関する行為
五 作業又は労務の請負
六 出版、印刷又は撮影に関する行為
七 客の来集を目的とする場屋における取引
八 両替その他の銀行取引
九 保険
十 寄託の引受け
十一 仲立ち又は取次ぎに関する行為
十二 商行為の代理の引受け
十三 信託の引受け
(附属的商行為)
第503条 商人がその営業のためにする行為は、商行為とする。
2 商人の行為は、その営業のためにするものと推定する。