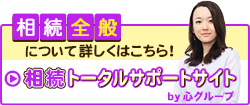1 破産の手続き中のギャンブル
自己破産は、裁判所に申立てをしたうえで免責許可決定が出ると借金がなくなります。
そして、破産法は「免責不許可事由がなければ免責許可決定を出さなければいけない」という制度になっています。
そして、この免責不許可事由にはギャンブルが含まれます。
これは、破産手続きを始める前のギャンブルですら免責不許可事由であるため、破産手続中のギャンブルが特に厳しくみられるのは当然です。
もっとも、「ギャンブル=免責不許可事由=免責許可決定が出ない=借金がなくならない」とはなりません。
2 破産手続き中のギャンブルのデメリット
破産の審査としては、管財事件と同時廃止事件の2種類があります。
管財事件の場合、裁判所が選任した弁護士である管財人が、破産者の財産を調査したり、過去の経緯から免責を認めてよいか調査したりします。
管財事件のデメリットとして代表的なものは、以下の3つがあります。
①審査が長引く
②管財人との面談、裁判所での債権者集会への出頭が必要になる
③予納金で最低でも20万円支払わなければならない
弁護士の介入後にギャンブルを行った場合は、まず間違いなく管財事件となるため、これらのデメリットが付いてきます。
また、ギャンブルで費消した金額は、本来であれば債権者の返済に回せた金額であるとして、その補填を求められることもあります。
債権者への返済の原資を「破産財団」といい、その補填を「財団組入れ」と言います。
3 ギャンブルをしても免責にはなりうる
破産手続き中のギャンブルは、最悪のケースは免責不許可となりますが、免責になるケースも数多くあります。
特に、
①破産手続への真摯な態度での協力
②速やかな資料提出
③裁判所、管財人からの質問に対する誠実な回答
④財団組入れ
等をしっかりと行えば、むしろ免責不許可となる方が稀です。
逆に、これを怠ると本当に免責不許可になってしまうので、裁判所や弁護士の指示にしっかり従うことが大切です。
4 ギャンブルをしてしまったら、弁護士に話すべきか
これは、「絶対に話すべき」です。
自身が依頼した弁護士は、どうひっくり返っても依頼者の味方です。
破産者の生活指導も弁護士の責務であるため、厳しいことを言うこともありますが、それも結局は破産手続きが速やかに終わるためという依頼者のための助言です。
過ちを犯したとしても、それを真摯に打ち明ければ弁護士は必ず悪いようにはしません。
また、ギャンブルをしたことは、裁判所には絶対にバレます。
裁判所は1年間に何万件もの破産事件を見てきているので、現金でギャンブルをしたとしても、収支が合わなくなるため、確実にバレます。
ギャンブルをしておきながら、それを隠して後でバレると、本当に免責不許可になりかねません。
もし、間違ってギャンブルをしてしまっても、弁護士に相談して、破産が無事に終わるまでの計画を練り直すのが一番良いです。