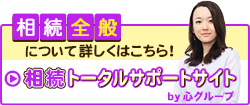1 令和の民法改正で新設された制度
「遺産分割前の相続預金の払戻し制度」とは、民法改正で新たに始まった制度で令和2年から利用できます。
通常、死亡した人の預金は凍結されてしまい、相続人全員で話し合って預金の分け方を決めないと、預金を引き出すことができなくなってしまいます。
しかし、この制度を使うと、相続人同士が揉めてしまい話し合いがつかなくとも、1銀行あたり最大150万円まで預金を引き出すことができるため、葬儀費用や相続税の支払いに充てることができます。
2 銀行1つにつき、最大150万円引き出せる。
引き出しに限度額が設定されています。
限度額は、銀行ごとに設定されていて、次の①②のうち低い方の金額を引き出すことができます。
① 預金額(※)×法定相続分×1/3
② 150万円
(※)預金額は、その銀行の全ての預金口座を足した金額になります。
実際に、相続人の人数や持っている口座の数・金額によって引き出し可能額が変わるので、具体例で説明します。
例1)
相続人:子供2人(法定相続分1/2)
持っている口座
①横浜銀行 普通預金 200万円
②横浜銀行 定期預金 400万円
③みずほ銀行 普通預金 1200万円
↓
①②横浜銀行から合計100万円
【200万円+400万円(預金額)×1/2(法定相続分)×1/3】
③みずほ銀行から150万円
【1200万円(預金額)×1/2(法定相続分)×1/3>150万円】
合計 250万円
【解説】
①②の横浜銀行は、預金額が横浜銀行全体の預金額が合計600万円なので、これに法定相続分の1/2と法律で決められた割合である1/3をかけると100万円となります。
100万円は、もう一つの限度額の150万円以下なので、低い方である100万円を引き出すことができます。
③のみずほ銀行は、
預金額が横浜銀行全体の預金額が1200万円なので、これに法定相続分の1/2と法律で決められた割合である1/3をかけると200万円となります。
しかし、200万円は、もう一つの限度額の150万円以上になってしまうので、低い方である150万円を引き出すことができます。
例2)
相続人:兄弟5人(法定相続分1/5)
持っている口座
①三菱UFJ銀行 普通預金 6000万円
↓
①三菱UFJ銀行から150万円
【6000万円(預金額)×1/5(法定相続分)×1/3>150万円】
合計 150万円
【解説】
①の三菱UFJ銀行は、預金額が6000万円なので、これに法定相続分の1/5と法律で決められた割合である1/3をかけると400万円となります。
400万円は、もう一つの限度額の150万円以上になってしまうので、低い方である150万円を引き出すことができます。
例2は、預金額だけで言えば例1(1800万円)より多いですが、引き出しが銀行1つあたり150万円となってしまうため、三菱UFJ銀行1つしかないと、横浜銀行とみずほ銀行の2つの銀行から引き出せる例1より少なくなってしまいます。
3 相続預金の払戻し制度の手続き方法と必要書類
手続方法は、銀行ごとに異なりますが、大きな流れはどこも同じです。
① 死亡したことの銀行への連絡
② 銀行からの必要書類の案内
③ 必要書類の提出
④ 預金の払戻し
そして、必要書類としては、概ね次のような書類が必要になります。
・被相続人の出生から死亡までの全ての戸籍
・相続人全員の戸籍
・銀行所定の書類(ex.相続手続依頼書)
・手続をする人の印鑑登録証明書(有効期限あり)
・手続きをする人の身分証明書
まずは、銀行の支店の窓口に連絡するか、銀行のホームページにある相続相談窓口に死亡した旨を伝えると、手続きがスタートになります。
また、手続きそのものを専門家に依頼してしまうのも一つの手でしょう。